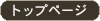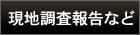|
キーワード: |
サンガ、帰依の対象となるサンガ、釈尊を和尚とするサンガ、各地に散在する個別のサンガ、釈尊教団 |
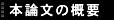
[目次]
緒 言 .................. 005
【1】律蔵の体系 .................. 011
[1]律蔵全体が随犯随制されたのではないこと
[2]波羅提木叉の体系
[3]比丘の定義
[4]波羅提木叉の条文と犍度部との関係
[5]捨堕以下の条文と犍度部の内容上の相関関係
小結
[1]具足戒の種類
[2]「律蔵」における各種具足戒の制定場面
[3]「律蔵」の比丘、比丘尼の定義
小結
[1]僧宝の成立
[2]「善来比丘具足戒」の始まり
[3]法宝の成立時期
[2]「三帰依具足戒」制定に関する基本的問題
[3]ウルヴェーラ・カッサパの教化
[4]三迦葉の教化の後の釈尊の動き
[5]ウルヴェーラーとガヤーシーサ滞在期間
小 結
[1]「十衆白四羯磨具足戒」の制定因縁の導入部
[2]「十衆白四羯磨具足戒」の制定因縁
[3]羯磨というもの
[4]「十衆白四羯磨具足戒法」の制定
[5]「十衆白四羯磨具足戒法」の制定年
[6]5年依止規定の制定
[1]出家資格審査項目
[2]十遮十三難の制定因縁の概観
[3]「五種の病気」など資格審査各項目の制定年
[4]「受戒犍度」以外の犍度の制定年
[1]摩訶迦旃延の生涯の主な事績
[2]持律第五具足戒の制定年
[1]マハーパジャーパティー・ゴータミーの具足戒
[2]比丘尼の具足戒
[1]ヴェーランジャーでの雨安居記事
[2]マドゥラーへの遊行とヴェーランジャーでの雨安居
[3]波羅夷罪第1条の制定因縁
[4]ヴェーランジャーでの雨安居年と波羅夷罪第1条の制定年
[1]波羅夷罪第2条「盗戒」の制定因縁
[2]波羅夷罪第3条「殺人戒」の制定因縁
[3]波羅夷罪第4条「大妄語戒」の制定因縁
[4]波羅夷罪第2、第3、第4条の制定年
本稿はサンガの形成と発展過程を縦糸として、これに横糸のようにからむ律蔵の諸規定がどのように制定されていったかを考察しようとしたものである。
縦糸であるサンガの形成と発展過程というのは、換言すれば具足戒法の制定過程であり、具足戒法の制定過程とサンガの形成・発展過程は次のような関係となる。
五比丘が善来具足戒を受けて比丘となり阿羅漢となったこと=三宝帰依の対象としてのサンガの成立
三帰依具足戒法の制定=サンガ祖形の成立
十衆白四羯磨具足戒法の制定=サンガの成立
二部僧白四羯磨具足戒法の制定=比丘尼サンガの成立
持律第五白四羯磨具足戒法の制定=サンガの地方への展開
また横糸たる律蔵の諸規定というのは、上記の具足戒法の制定を記す「受戒犍度」の外の、『パーリ律』でいえば19に上るさまざまな犍度に盛り込まれた規定であり、また4つの波羅夷罪を初めとする波羅提木叉の諸規定のことである。
この結論を年表のような形でまとめると次のようになる。「年齢」は釈尊の出胎を誕生日とする満年齢、「成道」は成道年の意味で、成道日から次の成道日前日までを1年とし、「期」は成道日から雨安居(雨期)を過ごすまでを前期とし、雨安居の翌日から次の成道日の前日までを後期とする。古代中国暦を用いて成道日を2月15日とすると、前期は2月15日から8月15日までの6ヵ月間、後期は8月16日から2月14日までの6ヵ月間ということになる。なお「期」は前期、後期2期に分けるが、前期中には雨安居が含まれ、特に「雨安居」としたものもある。「雨安居中」という意味である。
| 年齢 | 成道 | 期 | 記 事 |
| 35 | 1 | 前期 | 釈尊が成道して帰依の対象となる「仏宝」と「法宝」が成立する。 |
| 後期 | 五比丘が善来比丘具足戒を受け、後に阿羅漢となって世界に阿羅漢が6人 存在することとなった。これによって帰依の対象としての「サンガ」(僧 宝)が成立する。 | ||
| 36 | 2 | 前期 | ヤサとその54人の友人たちが阿羅漢となり、阿羅漢は世界に61人とな る。 |
| 後期 | 仏弟子たちを諸国に布教に出し、釈尊自らはウルヴェーラーに行く。 | ||
| 後期 | ウルヴェーラ・カッサパの教化を続けながら冬を過ごす。 | ||
| 37 | 3 | 前期 | ウルヴェーラ・カッサパの教化を続けながら雨期を過ごす。 |
| 後期 | 雨期が終わったころウルヴェーラ・カッサパが帰信し、続いてナディー・ カッサパ、ガヤー・カッサパとその仲間たちが帰信して善来具足戒を受ける。大人数の集団となったので釈尊は生活拠点をガヤーシーサに移す。 | ||
| 38 | 4 | カッサパ三兄弟とその仲間たちをガヤーシーサで教育しながら、諸国に布教に出た仏弟子たちが出家希望者を連れて帰ってくるのを待つ。(ガヤーシーサでの雨期第1年) | |
| 39 | 5 | カッサパ三兄弟とその仲間たちをガヤーシーサで教育しながら、諸国に布 教に出た仏弟子たちが出家希望者を連れて帰ってくるのを待つ。(ガヤーシーサでの雨期第2年) | |
| 40 | 6 | カッサパ三兄弟とその仲間たちをガヤーシーサで教育しながら、諸国に布教に出た仏弟子たちが出家希望者を連れて帰ってくるのを待つ。(ガヤーシーサでの雨期第3年) | |
| 41 | 7 | カッサパ三兄弟とその仲間たちをガヤーシーサで教育しながら、諸国に布教に出た仏弟子たちが出家希望者を連れて帰ってくるのを待つ。(ガヤーシーサでの雨期第4年) | |
| 42 | 8 | カッサパ三兄弟とその仲間たちをガヤーシーサで教育しながら、諸国に布教に出た仏弟子たちが出家希望者を連れて帰ってくるのを待つ。(ガヤーシーサでの雨期第5年) | |
| 43 |
9 |
前期 | カッサパ三兄弟とその仲間たちをガヤーシーサで教育しながら、諸国に布教に出た仏弟子たちが出家希望者を連れて帰ってくるのを待つ。(ガヤーシーサでの雨期第6年) |
| 後期 | 仏弟子たちが疲れ果てたので、「三帰依具足戒法」によって仏弟子が出家希望者に具足戒を与えることを許し「サンガの祖形」が形成される(ただし『五分律』などはこれを認めない)。しかし新参比丘の教育制度が整備されなかったため、比丘の威儀が乱れることになる。 | ||
| 44 | 10 | 前期 | (成道10回目の雨期の前の酷暑期)王舎城に行きマガダ国王ビンビサーラとマガダ国人を教化し、ビンビサーラから竹林園を寄進される。(釈尊の教えがインド社会において公認される) 舎利弗・目連とその仲間たちが帰信し、善来具足戒を受ける。 |
| 46 | 12 | 後期 | 比丘の威儀が乱れていることに対する非難の声が上がり、これをきっかけとして和尚と弟子の制=「十衆白四羯磨具足戒法」が制定され、「サンガ」が形成される。(三帰依具足戒法は廃止) 同時に「十遮十三難」中の多くの受具足戒資格審査項目も定められる。 このころに布薩と雨安居の制が制定され、竹林園に僧院が建てられる。 |
| 48 | 14 | 前期 | 浄飯王の願いをきっかけに、父母の許可を得なければならないという出家資格審査項目が定められる。 |
| 前期 | 給孤独長者により舎衛城に祇園精舎が建立され、「釈尊教団」に寄進される。 | ||
| 53 | 19 | 後期 | 迦絺那衣の制度が制定される。 |
| 54 | 20 | 後期 | 満20歳以上という受具足戒資格審査項目が定められる。 |
| 56 | 22 | 雨安居 | ヴェーランジャーで雨安居を過ごす。 |
| 57 | 23 | 前期 | 波羅夷罪第1条(婬戒)が制定される。 |
| 雨安居 | 波羅夷罪第3条(殺人戒)が制定される。 | ||
| 後期 | 波羅夷罪第4条(大妄語戒)が制定される。 | ||
| 後期 | (第23回目の雨安居をヴェーサーリーで過ごされた後、王舎城において)波羅夷罪第2条(盗戒)が制定される。 | ||
| 58 | 24 | 後期 | マハーパジャーパティー・ゴータミーが最初の比丘尼となる。 |
| 61 | 27 | 後期 | 「二部僧白四羯磨具足戒法」が制定され、「比丘尼サンガ」が成立する。 |
| 62 | 28 | 前期 | マハーカッチャーナがアヴァンティ国に布教し、ソーナ・クティカンナが沙弥として出家する。 |
| 後期 | 聡明有能な比丘に対する5歳依止規定が制定される。 | ||
| 65 | 31 | 前期 | ソーナ・クティカンナが具足戒を得て比丘となる。 |
| 後期 | 地方での「持律第五白四羯磨具足戒法」が許され、釈尊教団が地方に発展する基礎となる。 | ||
| 69 | 35 | 後期 | 最初の「破サンガ」が起こり、「コーサンビー犍度」が説かれる。 |
| 72 | 38 | 後期 | 提婆達多の破サンガ(ブッダへの反逆)が起こり、「破僧犍度」が説かれる。 |