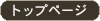|
キーワード: |
Janapada Raṭṭha 国 部族 ガーマ ニガマ ナガラ 王 ゲマインシャフト ゲゼルシャフト |
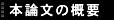
我々が発行しつつある資料集「原始仏教聖典の仏在処・説処一覧」は、仏典に伝えられる十六大国(soḷasa mahājanapada)をイメージして、原始仏教聖典の経蔵・律蔵にわたる仏在処・説処のすべてを、国ごとに整理しようとするものである。マガダ国篇、コーサラ国篇が終わり、これらに続くその最終作業である「その他国篇」を整理する段階に至って、次のような問題が生じてきた。すなわち、十六大国にもさまざまな伝承があって、それらをどのようにアイデンティファイするべきかという問題や、かなり資料数の多い釈迦国などを、十六大国に含まれないからといって独立させなくてもよいかという問題などであって、具体的に言えば、われわれが「その他の国篇」として整理しようとする「国」をどのように定義し、そしてどのような「国」を項目として立てるべきかという問題である。
そこでパーリ仏典において「国」を表すのに用いられるjanapadaとraṭṭhaを調査することになった。しかしこれらの言葉を子細に調査してみると、単に「国」の中の一地域や一地方をさす場合や、極端にいえば町や村をさす場合もあることが判明した。そのような経緯からjanapadaとraṭṭhaを正確な概念づけをすることが必要となり、両語に含まれる外延や背景、あるいは歴史的経緯による用例の変化などを追及することになった。これが本論文の制作動機である。以下、その結論を示すと次のようになる。
janapadaは「人々」を意味するjanaと、「足」を意味するpadaの合成語であって、「人々」が「足を踏み入れた土地」を原義とする。このような土地とは「開発された」土地ということであって、英語で言えばcultivateされた土地ということになる。しかもjanaはインドの古代においては「部族の人々」をさすので、janapadaはその原義を「部族の人々が住む土地」と解釈できる。またこのような土地は、幾世代にもわたって継承されるから、その土地には血縁地縁に結びついた社会が形成されることになり、またいつしかその土地独自の生活慣習や宗教的儀礼あるいは言葉(方言)もでき上がることになる。したがってjanapadaに形成される社会は、人間の本質的な営みに付帯して自然的に形成されるGemeinschaft的社会ということになる。
一方のraṭṭhaは「支配する」を意味する√rājという動詞を語源とするから、これは支配・統治ということを目的として人工的に形成されるGesellschaft的社会ということができる。また√rājは「王」を意味するrājanの語源であって、この王がraṭṭhaを支配する。したがってraṭṭhaの原義は「王の支配する王国」ということになり、その「王国」は「国」という社会組織的なものとその領土を含む意となる。
このようにjanapadaとraṭṭhaは語義の上からは対照的なものを有するが、現実的に指し示すものには共通する部分もある。janapadaのjanaを「マガダ人」や「コーサラ人」ととらえればjanapadaは「マガダ人が住むところ」や「コーサラ人が住むところ」というように、かなり広い範囲をさすことになるし、janaを「バーラーナシー市に住む人々」「ルンビニー村に住む人々」というようにとらえれば、janapadaは「バーラーナシー」という都市や、ルンビニーという村という狭い範囲を指すことにもなる。またjanapadaは付帯的に「janapadaに住む人(jānapada)」を意味する場合もあるから、「国民」とか「地方民」という訳語が与えられることになる。なおjanapadaに「大」を意味するmahāを付けて「大国」と呼ばれる場合は、普通のjanapadaを複数包括するものであって、janapadaが「国家」とよばれうる場合は、周辺に広がるニガマ(複数の集落の居住民が利用する商工業者の住む地域)やガーマ(集落)の行政機能を有した複数のナガラ(城壁で囲まれた地方行政官や商工業者が住む地域。市)を包括するものと考えてよい。
一方のraṭṭhaもその「支配」の内容をどのレヴェルでとらえるかによって、たとえば付傭国であったアンガもraṭṭhaであったし、理論上は宗主国であったマガダもraṭṭhaということができる。しかし原始仏教時代にはまだ組織的な王制が十分に発達しておらず、したがってマガダやコーサラという「大国」がraṭṭhaと称される用例はない。これが現れるのは注釈書文献になってからであり、その用例は【9】「歴史的経緯によるjanapadaとraṭṭhaの用法の変化」で示した通りである。また「王」にもマガダやコーサラというような「大国」の王もあったけれども、いわゆる藩王や町や村を支配する中間層の王も存在したから、raṭṭhaの指し示す領域はさまざまであって、したがってjanapadaと同様に「国」とか「地方」などという訳語が与えられることになる。またraṭṭhaも「raṭṭhaに住む人」を意味する場合もあったから、これにも「(王に対する)国民」とか「地方民」という訳語が与えられることになる。
しかし用例を細かく調べてみると、janapadaとraṭṭhaには相違も見いだされる。janapadaは自然に形成されたGemeinschaft的社会を土台とするから、その領域をはっきりとどこからどこまでと限定することができない。そこでインド半島の中央地方とか辺境地方、あるいは雪山地方などというように、漠然とした「地域」を指し示すこともできる。一方のraṭṭhaは支配という権限がおよぶ人工的な社会をいうから、「領土」という語感がピッタリとし、これにははっきりとした境界線が設けられる。したがってある一定の地域を漠然とraṭṭhaと呼ぶことはない。またjanapadaは本来は原野やゴーストタウンのような「人が住まない土地」は含まず、血縁地縁的な色彩の強い「開墾された土地」をそもそもの原義としたものであったから、どちらかといえば人工的な色彩の強い都市や町に対して「田舎」をさす場合もある。しかしraṭṭhaにはこのような意味は与えられない。
janapadaとraṭṭhaは上記のようなものであるから、ある特定の地域をGemeinschaft的にとらえてjanapadaという場合もあれば、同一の地域が一人の王によって支配されていれば、その地域はraṭṭhaとも呼ばれうる。このようにjanapadaとraṭṭhaは重複しあうことがあると同時に、一つのjanapadaを2人の王が分割して統治することになれば、この場合はjanapadaの方がraṭṭhaよりも大きな範囲となり、あるいは二つのjanapadaを1人の大王が統治することになれば、この場合はraṭṭhaの方がjanapadaよりも大きいということになる。ただし「GemeinschaftからGesellschaftへ」という社会科学的な図式に当てはめれば、原始仏教時代のインドの社会は未だjanapada的な要素が強く、raṭṭha的認識は十分に発達していなかった。したがって「十六大国」と称されるマガダやコーサラなどはjanapadaといわれており、janapadaの方がraṭṭhaよりも広い範囲を指す場合の方が多かったといえる。しかし注釈書時代になると、すでにGesellschaft的社会になっており、マガダやコーサラなどの大国はraṭṭhaと称されるようになり、raṭṭhaの方がjanapadaより広い範囲を指すようになる。インドの国々は部族共和制的な国家から、王の専制君主的な国家に変質していたのである。
なお以上の論考によって、われわれが資料集「原始仏教聖典の仏在処・説処一覧」の「その他の国篇」を作成するにあたっての「国」と認めてよい基準は以下のようにまとめられる。
(1)十六大国として上げられている「国」
(2)janapadaの複数形で表される複数のナガラやニガマ、ガーマを含む「国」
(3)注釈書文献になってraṭṭhaと記されるようになる「国」
である。